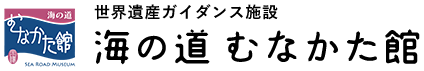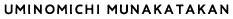更新日:2023年4月26日
今回は、みなさんの身近に存在するお堂のお話です。市内を歩くと、道端に神仏を祀ったお堂や祠など、今に息づく信仰の場を目にします。そこには、食べ物や花を供えるなどの祈りを感じられる活動があります。このようなお堂の多くは、宗像四国霊場の札所になっています。これらは、旅をする機会が限られていた江戸時代、今から約160 年前の幕末の頃に創られたもので、弘法大師ゆかりの「四国八十八ヶ所霊場」を手本に、供養や修行のための巡礼が身近な場所でもできるようにと、各地に広まった地方霊場のひとつです。
明治の終わり頃には札所設置の要望が多くなったため、釣川を境に東西に霊場を分けたり、太平洋戦争の影響で衰退したりと盛衰を繰り返し、今日に至っています。盛時には、弘法大師の分身とされる金剛杖を持ち、白衣と菅笠をまとったお遍路さんが、ご詠歌を唱えながら列をなして歩く姿が春と秋の風物詩になっていました。現在では東部霊場のみとなり、春に団体参拝が行われています。これらのほかにも、宗像 市には歴史を物語る「もの」 や「こと」などが今もなお数多く残っています。一方で、 少子高齢化など社会状 況の変化を理由に存続の危機にも直面しており、 これらをどのようなかたちで次世代に受け継いでいくのか、いま一度考える時期を迎えています。
明治の終わり頃には札所設置の要望が多くなったため、釣川を境に東西に霊場を分けたり、太平洋戦争の影響で衰退したりと盛衰を繰り返し、今日に至っています。盛時には、弘法大師の分身とされる金剛杖を持ち、白衣と菅笠をまとったお遍路さんが、ご詠歌を唱えながら列をなして歩く姿が春と秋の風物詩になっていました。現在では東部霊場のみとなり、春に団体参拝が行われています。これらのほかにも、宗像 市には歴史を物語る「もの」 や「こと」などが今もなお数多く残っています。一方で、 少子高齢化など社会状 況の変化を理由に存続の危機にも直面しており、 これらをどのようなかたちで次世代に受け継いでいくのか、いま一度考える時期を迎えています。
(文化財職員・山田)
このページに関するアンケート
このページに関する問い合わせ先
世界遺産課 文化財係
場所:海の道むなかた館
電話番号:0940-62-2600
ファクス番号:0940-62-2601